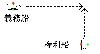お酒について ( 続き )
[ 7 : ウイスキーについて ]ウイスキーが日本に初めてもたらされたのは、嘉永 6 年 ( 1853 年 ) に アメリカの ペリー艦隊が来航 した際に、幕府に献上したのが始まりとされます。 その後 日米修好通商条約の締結に基づき、当時半農半漁 ( はんのうはんぎょ )の寂しい横浜村の港が 1859 年 に外国に開港されました。
現在 横浜港にある 大桟橋 ( おおさんばし ) ・ 国際客船 ターミナル の付近に東西 二箇所の波止場 ( はとば、埠頭 ) が建設され、多くの イギリス人が来日して外人商館が軒を連ねましたが、その際に彼らの飲料用として ウイスキーが持ち込まれ、日本人の間にも徐々に洋酒に対する関心が増えました。
右の写真は平成 14 年 ( 2002 年 ) に、リニューアル オープンしたものです。 ( 7−1、 ウイスキーの歴史 ) 日本における ウイスキー製造の歴史をたどると、現在の サントリー と ニッカ が歩んだ道につながります。ウイスキーが初めて日本に輸入されたのは、明治 4 年 ( 1871 年 ) のことでしたが、輸入元となったのは 薬酒問屋で需要はあまり伸びませんでした。明治の末期 ( 1912 年 ) には アルコールで合成した ウイスキーの模造品が日本で製造 ・ 販売されましたが、ウイスキーと呼ぶには ほど遠い品質でした。 広島県竹原町( 現 ・ 竹原市 ) の造り酒屋の三男で、後に ニッカ ウイスキーの創業者 となった 竹鶴政孝 ( たけつる まさたか、1894〜1979 年 ) がいましたが、大阪高等工業 ( 現 ・ 大阪大学 ) の醸造学科に学び当時大阪にあった摂津酒精 ( しゅせい、アルコールのこと ) 醸造所に入社しました。
1918 年 ( 大正 7 年 ) に社長の命を受けて単身 スコットランドに赴き、古都 エジンバラ ( Edinburgh )の西 60 キロ にある グラスゴー ( Glasgow ) の大学で有機化学と応用化学を学びましたが、1920 年に スコットランド人の医師の娘である リタ と結婚し 3 年間の留学を終えて 1921 年に彼女を連れて帰国しました。 その後竹鶴は会社から独立して北海道 ・ 小樽市近郊の 余市 ( よいち ) に ウイスキー蒸留所の設立を試みましたが、資金難のため最初は失敗しました。大正 12 年 ( 1923 年 ) に大阪の 寿屋 ( ことぶきや、現 ・ サントリー ) が本格 ウイスキーの国内製造を始めることになり、社長の 鳥井信治郎 ( とりい しんじろう ) の招きに応じて寿屋に入社しました。 竹鶴は大阪近辺の候補地の中から、良質の水が使え、スコットランドの著名な ウイスキーの産地 ローゼス の風土に似ていて、霧が多いという条件から大阪府 ・ 三島郡 ・ 島本町 ・ 山崎を蒸留所の候補地に推し、工場および製造設備は竹鶴が設計し、自らは工場長になりましたが 1923 年のことでした。国産 ウイスキーの本格的製造が始まったのは翌年の 1924 年からでしたが、明治初年に ウイスキーが輸入されてから約 50 年後のことでした。 山崎蒸留所での操業開始から 10 年が経過し生産が軌道に乗ったので竹鶴は 1934 年に退社独立し、自身の夢であったさらに本格的な スコッチ ウイスキーの製造を目指して、スコットランドと気候が似ている北海道 ・ 余市郡 ・ 余市 ( よいち ) 町に今度は 「 大日本果汁株式会社 」 を設立しました。 ウイスキーは製造してから樽に詰めて 「 熟成させる 」 ために出荷までに数年かかるので、その間の収入を得るために、 同時に リンゴジュースの製造もおこないましたが、彼が余市で ニッカ ウイスキーの出荷 ・ 販売を始めたのは 1940 年のことでした。 ( 7−2、名前の由来 ) 社名や商品名の ニッカ とは 「 大日本果汁 」 の 日果 から名付けられたものですが、竹鶴政孝が スコットランドから日本にもたらした ウイスキーの製造技術、具体的には蒸留技術 ・ ブレンド ( 混合 ) 方法 ・ 熟成方法などから、彼は後に 日本の ウイスキーの父 と呼ばれました。 リタ ( 1896〜1961 年 ) は 65 才で、竹鶴政孝 ( 1894〜1979 年 ) は 85 才でこの世を去りましたが、二人の墓は小樽近郊にある ニッカ ウイスキー 余市 ( よいち ) 蒸留所を見下ろす丘に建てられています。
ところで サントリー の名前の由来については、前身の寿屋 ( ことぶきや ) が 1907 年から 「 赤玉 ポート ワイン 」 を製造 ・ 販売していましたが、右図の ラベル の 赤玉 が太陽に見えるということで、英語の Sun 「 サン 」 と、創業者で社長の鳥井信治郎の姓から 「トリイ」 を採り、1929 年に発売した ウイスキーを サントリー と名付けました。 しかし 赤玉 「 ポートワイン 」 の名前が、 古くから ポルトガル 第 二の港湾都市である ポルト ( Porto ) 港から積み出された ポルト ワインを意味すると ポルトガル から クレイム を付けられたので、現在では、赤玉 スイート ワイン と改名して販売しています 。 [ 7−3、コフィー ブレイク ( Coffee Break )、ひと休み ]
ところで左図は船を正面から見た場合の航海灯ですが、飛行機と同様に船の航海灯 ( Navigation Light ) は左舷 ( ポート、Port ) 側が赤灯、右舷 (スターボード、Starboard ) 側には青灯 ( 緑灯 )を点灯させます。さらに前部 マストには白色灯 ( 低い位置 ) ・ 全長 50 メートル 以上の大きい船は後部 マストにも白色灯 ( 後方の高い位置 ) を点灯しますが、これ以外にも船尾には白色の船尾灯を点灯させます。
右図は二つの船が互いに 90 度近くの角度で針路が交差する場合の、海上衝突予防法第 15 条に規定した 「 横切り船 」 の、夜間における航海灯の見え具合ですが、船も飛行機同様に右側通行なので 相手の 赤灯 ( 左舷の航海灯 ) を見る船は、「 避航船 」 として相手を避ける義務 があります。
それに対して 相手の青灯 ( 緑灯 ) を見る船は、 「 保持船 」 なので 針路 ・ 速力を保持します 今年でちょうど 60 年前の海上保安大学 1 年の時 ( 1952 年 ) に、航海灯の左右の色を間違えないように、 「 赤玉 ポートワイン 」 つまり 赤灯 は ポート ( Port、左舷 ) と習いましたが、甘味果実酒 ( 果実酒に糖類または ブランデーなどを混和したもの ) である 「 赤玉 ポートワイン 」 の甘い味と共に、今もその言葉を忘れずにいます。
東海道線 ( JR 京都線 ) に乗ると、京都府 ・ 乙訓郡 ( おとくにぐん ) ・ 大山崎町にある山崎駅付近で、あるいは東海道新幹線の新大阪と京都間で北側の車窓から サントリー 山崎蒸留所 ( Suntory Yamazaki Distillery ) の看板がよく見えますが、先月 ( 4 月 ) にも新幹線に乗る機会があったので車窓から見ると、サントリー 蒸留所の別の建物にある Since 1923 と記した看板の文字が見えました。 ( 7−4、スコッチ ウイスキー ) スコッチ ・ ウイスキー ( Scotch whisky ) とは、ご存じのように スコットランド産の ウイスキーのことですが、1990 年の スコッチ ・ ウイスキー 令 ( The Scotch Whisky Order 、 第 3 条 ) によれば、その定義を以下のように定めています。
注:)
ところで昭和 30 年代初めの日本で最も有名な スコッチ ウイスキー は ジョニ 黒 と呼ばれていた ジョニー ウオーカー( Johnnie Walker ) の黒 ラベルでしたが、値段は大卒 サラリーマンの初任給と同じ 1 万円 前後でした。
私は昭和 32 年 ( 1957 年 ) の 1 月に アメリカ海軍飛行学校に入学のために羽田空港から渡米しましたが、アメリカの リカー ストア ( Liquor Store 、酒屋 ) ではそれが僅か 5 ドル ( 当時は 1 ドル = 360 円の固定 レート、1,800 円 ) で売っていたので、その安さに驚きました。 前述した サントリー や ニッカ を保護するためと、敗戦後の日本が貧しく 慢性的な外貨不足 のために、贅沢品 ( ぜいたくひん ) の外国産高級 ウイスキー に 220 パーセント という高い従価税を課けて輸入制限をしていたからであり、日本人が自由に海外へ旅行できるようになったのは、国際収支の黒字が拡大した昭和 39 年 ( 1964 年 ) からでした。
その当時から昭和 60 年 ( 1985 年 ) 頃までは、海外出張や海外旅行から帰国する人たちは 免税 ( DUTY FREE ) の範囲である、 外国産 ウイスキー類なら 3 本 を手に下げて帰るのが定番の スタイルでしたが、輸入関税が大幅に引き下げられた今ではその姿も見られなくなりました。 ウイスキーは ブランデー ・ ウオッカ ・ 焼酎 ・ 中国の白酒 ( ぱいちゅう ) などと同様に 、発酵させた大麦の麦芽醪 ( もろみ ) や醸造液を更に蒸留して アルコール濃度を高めた、いわゆる蒸留酒 ( スピリッツ、Spirits ) の 一種ですが、材料としては大麦 ・ ライ麦 ・ トウモロコシなどを麦芽 ( ばくが ) の酵素で糖化し、これに酵母 ( モルト、 Malt ) を加えて発酵させたのち、蒸留して造ります。 ウイスキーの主な生産国は日本の外に イギリス ( スコットランド ) ・ アイルランド ・ カナダ ・ アメリカですが、国によりその製造方法に差があるものの、日本の ウイスキーは スコットランドとほぼ同じ方法で造られています。ウイスキー製造の歴史はワイン ・ ビール ・ 酒などと比べてかなり新しく、ウイスキーが歴史上はじめて文献に登場したのは、1405 年の アイルランドであり、スコットランドでも 1496 年に記録が残っていますが、その理由は 蒸留の技術 を必要としたからでした。 ( 7−5、蒸留とは ) 蒸留の定義とは液体を熱して気化させ、その気体を 冷却して再び液体にすること ですが、不純物が除かれて純粋な液体が得られます。 ウイスキーなどの蒸留酒を造る際には、水と アルコールの 沸点 ( ふってん、沸騰し始める温度 ) の差を利用します。 1 気圧の場合水は摂氏 100 度で沸騰 ( ふっとう ) しますが、アルコールの沸点はそれよりも低く摂氏 78.3 度 で沸騰します。そのために アルコール分を含む液体を 100 度近くに加熱すると蒸気が発生しますが、この蒸気には元の液体の アルコール分が含まれています。 この蒸気を冷却すれば、元の液体よりも アルコール濃度の高い液体を得ることができますが、この蒸気発生と 冷却の過程を何度も繰り返すことにより、更に アルコール濃度の高い液体を得ることができます。
単式蒸留器 ( シングル ・ ポット ・ スティル、Single Pot Still )では 1 回の蒸留で アルコール濃度は 3 倍 にしか増えませんが、左の 多段式蒸留器 ( Patent Still、特許を取得した蒸留器 ) では アルコール濃度が非常に高い蒸留液を容易に得ることができます。 ( 7−6、アルコール濃度の表示 ) 日本では ビール ・ ウイスキー ・ 日本酒などの酒類の アルコール濃度を、 度数や ( % ) で表示 しますが、これは温度 15 度 C における容積濃度を 百分率で表示すると定められています。 例えば 35 ( % ) = 35 度とは液体 100 ml ( ミリ リットル ) 中に、エチルアルコールが 35 ml ( ミリ リットル )、 つまり 35 パーセント 含まれていることを示し国際基準と同じです。 これに対して イギリスや アメリカでは プルーフ ( Proof、保証 ) の単位を使うことがありますが、比重計の無い時代に火薬を アルコール濃度の高い蒸留酒で濡らし、火を付けて火薬が燃えることで アルコール濃度の 保証 ( Proof ) にしたことに由来します。
しかし紛らわしいのは アメリカの濃度単位である プルーフ が、容積比率である アルコール度数 ( % ) 値の 「 2 倍 」 であるのに対して、イギリスの プルーフ 値 は アルコール度数 ( % ) の 「 1.75 倍 」 であることです。 例えば右写真の トウモロコシ を原料にした ケンタッキー産の バーボン ウイスキー ( bourbon whisky) Early Times の ラベル表示には 40 % A L C / V O L ・ 80 PROOF と表示されていますが、その意味は アルコールの 容積濃度 ( Alcohol / Volume ) が 40 % であり、 80 プルーフ であることを示します。 しかしこの容積濃度 40 % を仮に イギリス流の表示にすれば、 70 プルーフ になります。
[ 8 : ワインの歴史 ]( 8−1、名前の起源 )ワイン ( Wine ) とは英語ですが、 フランス語では ヴァン ( Vin ) 、ドイツ語では ワイン ( Wein ) 、 イタリア語では ヴィーノ ( Vino )と言い、いずれも ラテン語の ヴィヌム ( Vinum 、ブドウを発酵したもの ) に由来すると思っていました。 ところが別の説によれば、古代 インドの紀元前 12 世紀 〜 前 10 世紀における ヴェーダ ( Veda ) 時代に、神に捧げられ 「 不死を約束する飲み物 」 である、神酒の ヴェーナ ( Vena 、サンスクリット語で愛される者 ) に由来する言葉であるとされました。興奮作用や幻覚作用をもたらす ヴェーナの原料は 「 ぶどう 」 ではなく、ある植物の汁を発酵させて造られたとされますが、今に至るまで原料は不明です。
ワインの原料となる ぶどうの 原産地 は、 ロシア南西部で黒海と カスピ海の間にある コーカサス ( Caucasus、カフカスともいう ) 地方や、 温帯西 アジア地方 とされますが、その栽培の歴史は紀元前 5,000 年にさかのぼるといわれています。 これらの地方から メソポタミアの周辺地域、および エジプトに ぶどうの栽培と共に ワインの製造法が伝えられ、やがて ギリシャを経て紀元前 3 世紀には地中海の覇者となった 都市国家 ローマに伝えられました。
その後 紀元前 27 年に興国した ローマ帝国が ワイン文化の中心となりましたが、その領土拡大とその後の 200 年に及ぶ パックス ・ ローマーナ ( Pax Romana 、Pax とは ラテン語で平和の意味であり、ローマの支配による地域の安定 ・ 平和の意味 ) に伴い、 ガリア( Gallia、現在の フランス ・ ベルギー ・ オランダなど ) を初め ヨーロッパ各地に ぶどう栽培と ワイン造りが広まりました。 人類が ワインをいつ頃から造るようになったのかは不明ですが、紀元前 4,000 年頃に チグリス川の中流域で生活していた シュメール人が、ワインを造り飲んだことが、この地方の都市国家 ウルク ( Urk )の ウル ( Ur ) 王墓や遺跡から発見されています。
左図は古代 エジプトにあった古代都市 テーベ ( 現在の ルクソール近郊 ) にある ナクト墳墓の壁画 ( 紀元前 1580 年 ) で、画面の右側には ぶどうの収穫の様子、左側には摘み取った ぶどうを足で踏んで圧搾 ( あっさく ) しているところ、中央には しぼった果汁を甕 ( かめ ) に入れる工程が描かれています。 11 世紀後半になると ワイン造りは キリスト教と密接に結びつき、修道院によって ぶどう栽培 ・ ワイン造りが積極的に行われるようになりましたが、さらに 15 世紀末から大航海時代が始まると、 スペイン人 ・ ポルトガル人 ・ オランダ人 ・ イギリス人などによって、次第に南北 アメリカ大陸、南 アフリカ、オーストラリアにまでぶどう栽培と ワイン造りが広がりました。 ちなみに ニュージーランドで ぶどうが最初に栽培されたのは 1819 年でしたが、人口が大阪府の半分に当たる 442 万人のところ、2009 年における ワイン生産量は世界の トップ 20 位で、 日本の 2.28 倍でした 。
[ 9 : 日本にもたらされた ワイン ] 日本に初めて ワインがもたらされたのは 16 世紀の中頃で、スペイン出身の宣教師 フランシスコ ・ ザビエル ( Francisco Xavier 、1506〜1552 年 ) が、キリスト教布教のために 1549 年に鹿児島に上陸し、山口 ・ 平戸などで宣教し 1551 年に離日しました。 その間に彼は 山口の領主であった大内義隆 ( よしたか ) に ヴィニョ ・ ティント ( Vinho tinto 、ポルトガル語で tinto は赤の意味で 赤 ワイン 、つまり当時の言葉で 珍陀酒 ( ちんた ざけ ) を献上したとする記録があります。 なお安土桃山時代 ( あずち ももやま じだい、1573〜1603 年 ) の覇者であった織田信長 ・ 豊臣秀吉も、その当時 ポルトガル および スペインとの間に行われた南蛮貿易によりもたらされた珍陀酒 ( ちんた ざけ ) を、賞味 ・ 珍重しました。 ( 9−1、ワイン造りの先駆者 ) 前述のように日本に ワインが伝えられたのは 16 世紀のことでしたが、日本で ワイン造りが始まったのは明治維新以後のことでした。明治政府は殖産興業政策の 一環として 欧米諸国を見習い、ぶどう栽培 ・ ワイン醸造振興策を加えましたが、その理由は当時の日本が米不足でしたので、米を原料とする酒造りを減少させるためでもありました。 政府は欧米から ぶどうの苗木を輸入し、山梨県をはじめ各地で ぶどう栽培と ワイン醸造を奨励しましたが、明治 5 年 ( 1872 年 ) 頃に甲斐国 ・ 甲府 ・ 広庭町 ( 現 ・ 山梨県 ・ 甲府市 ・ 武田三丁目 ) の 山田宥教 ( ひろのり )、と八日町 ( 現 ・ 甲府市 ・ 中央 二丁目 ) の 詫間憲久 ( たくま のりひさ ) の二人が共同でぶどう酒の醸造を始めましたが、山田宥教は広庭町の真言密教の大応院の法印 ( ほういん、僧の位 ) でしたので、日本で初めての ぶどう酒の醸造所は大法院の境内にあった土蔵を改装して使用したといわれています。 しかし 醸造技術の未熟やワインの原料となる ぶどうの糖度不足から、生産した ぶどう酒の品質があまり良くなく、それに加えて資金難から山田、詫間の共同醸造所は明治 9 年 10 月に倒産廃業してしまいした。その翌年の 8 月に今度は山梨県 ・ 東八代郡 ・ 祝村 ・ 下岩崎 ( 現 ・ 甲州市 ・ 勝沼町 ) の有志などにより 「 大日本山梨葡萄 ( ぶどう ) 酒 会社 」 が設立されました。 前述の山田 ・ 詫間組の失敗を繰り返さない為に、ワイン醸造技術と醸造法を完全に指導できる有能な人材が必要になりましたが、そこで祝村から優秀な青年 2 名を選び ワインの本場 フランスへ 1 年間派遣し、醸造技術とその施設の修得、さらに醸造用 ぶどうの品種の選別 などの知識や技術を徹底的に学ばせて、日本人の手による国産の良質な ぶどう酒を生産することにしました。
そこで祝村の 高野正誠 ( まさなり、25 才 ) と 土屋助二郎 [ 後の竜憲 ( たつのり )、19 才 ] の 2 名が選ばれて、明治 10 年 ( 1877 年 ) 10 月に パリに向け出発しましたが、パリから 150 キロ離れた シャンパーニュ 地方 オーブ県 ( 当時郡 ) トロワ市 ( 町 ) に下宿しました。 そこで専門家から ぶどうの剪定 ( せんてい )、挿 ( さ ) し木法、品種を改良するための 接ぎ木法、摘果 ( てきか ) 、収穫法の実技を習いながら品種改良と ヨーロッパ式の新しい栽培法や、生食用ぶどうと醸造用ぶどうの本質的な違いなどを実地で学びました。写真は土屋と高野で、パリの写真館で剪定 ( せんてい ) の ポーズを撮影。 彼らが ぶどうの収穫から ワインの貯蔵法、新酒の蔵出しまでの研修の過程を終えて帰国したのは、留学予定期間の 1 年を 7 ヶ月過ぎた明治 12 年 ( 1879 年 ) 5 月のことでした。 ( 9−2、山梨県の ワイン造り )
その時以来 日本における ワイン造りの中心は、山梨県の甲府市やその周辺となりましたが、現在も甲府市から約 10 キロ北西にある甲斐市 ( かいし ) には、サントリー登美( とみ ) の丘 ワイナリー ( Winery、ワイン醸造所 ) があり、ここ以外にも甲府盆地周辺には多数の ワイナリーがあります。写真は甲府盆地周辺に広がる ぶどう畑の向こうに、約 40 キロ離れた富士山が見える風景です。
[ 10 : 酒類消費数量の推移 ]下表の数値は国税庁統計年報によりますが、沖縄県の分は従来同様に含まれていません。平成 18 年 ( 2006 年 ) の酒税法改正により、これまでの焼酎 ( しょうちゅう ) 甲類 ( アルコール度数 36 % 未満 )が 連続式蒸留焼酎に名前が変更され、同じく焼酎 乙類 ( アルコール度数 45 % 以下 ) が 単式蒸留焼酎 に変更されました。
( 単位は 1,000 キロリットル )
[ 10−1、ソムリエ ]ソムリエ ( Sommelier ) とは辞書の大辞林によれば、「 高級 レストランの ワイン専門の ウエーター」、「 ワインに関する専門知識を持ち、客の相談に乗って ワインを選ぶ仕事をする 」 とありましたが、この職業が日本で知られるようになったのは 1970 年 ( 昭和 45 年 ) 代の半ば頃からで、高度経済成長の波に乗り生活に ゆとりができてきたので ワインへの関心が高まり、ソムリエの名称も徐々に一般の人々に浸透していきました。ソムリエは フランスでは国家資格ですが、日本ではなんの 法的資格も届け出も必要がない 点で遺体を扱う 葬儀屋と同じであり 、その気になれば 誰でも今日からでも ソムリエの仕事に就くことができます 。( 法律には少しも違反しません ) 葬儀屋には 「 葬祭 ディレクター制度 」 ( 1 級と2 級 )があるものの、この資格が無くても営業上は全く支障がありませんが、厚労省からの天下り役人の手土産に設けられた制度 ・ 資格だからです。料理に合う ワインを選びそれを注ぐ仕事をする ソムリエには、 ソムリエ 呼称資格認定試験 があり、社団法人 日本 ソムリエ協会が実施していますが、ワインについての専門的な知識と サービス技術があるかどうかを 協会が 認定するのだそうです。 呼称資格認定試験 は以下に分かれています。
そういえば航空会社の客室乗務員の中にも ソムリエ や ワイン なんとか の 「 呼称資格 」 を取るために講習を受講したり、受験用の学校に時々通う人もいましたが、呼称資格認定試験の受験資格に 「 OO 講習会を受講した人 」 という 集金制度の存在 が、やはり気になります。参考までに ソムリエの受験料は一般の場合 12,100 円、合格後の認定登録料は 20,000 円で、合格率は 41 % ( 2004 年 ) です。 この制度は例の交通安全協会に加入した ドライバーを対象にした 「 優良運転者表彰制度 」 と同様に、 あっても無くてもよい 一部の マニア向けの制度か 、あるいは 一部の人達による メシの タネ ・ 金儲けの制度 ではないことを願っています。 ちなみに前述した 「 葬祭 ディレクター制度 」 ( 1 級と 2 級 ) の受験料は それぞれ 5 万円と 4 万円ですが、なぜこれほど高額なのか 一説によれば、受験者がほとんど無く採算が取れない (?) からだそうですが、何百年も掛けてその地方に受け継がれ形成された葬式という社会の風習 ・ 習慣の分野に、今さら資格制度を導入することの無理がもたらした 本末転倒の話でした。
[ 11 : ワインについての、知ったかぶり ]
[ 12 : カエル と サル ] 9 世紀以降、ヨーロッパは キリスト教のもとで ワイン文化と 一体化して、王侯貴族たちは教会所有のぶどう畑で産する ワインを楽しみましたが、フランスでは 18 世紀末までどの地方でも ワインを自給自足していました。輸送が困難で時間を要し、遠方の市場まで送り出されるのは固有の販路を持つ特色ある ワインに限られていました。 ところが フランス革命で活躍した共和派の軍人 ・ 政治家の ジュルダン ( Jourdan ) が 1798 年に初めて近代的な徴兵制度を成立させましたが、兵役に服する兵士に対して食事の際に ワインを支給したこともあり、さらに 1832 年に フランスで鉄道の営業が開始されたために こうした輸送状況が改善されたことから、ワインは フランス人にとって国民的な飲み物になりました。 フランス人にとって ワインは食時の際の必需品と見なされるようになり、現在はどうか知りませんが 以前は エアー フランス の パイロット たちは、操縦席での食事の際にも小瓶の ワインを飲むといわれていました。
彼らによれば、
食事の際に水を飲むのは、 カエル ( la grenouille 、ラ グルヌイユ ) と アメリカ人だけだ。そうです。
これに対して フランス人に対する悪口は、カタツムリ ( Escargot ) だけでなく カエルも食べる ので、 Frog ( カエル ) とか、 ( Cheese-eating ) Surrender monkeys ( チーズを食べながら ) すぐに降伏する サル でした。 写真は調理前の カエルの食材です。
|